この記事の目次
はじめに
こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。
2月も残りあとわずかということで、3月決算の法人の社長や経理部長の方は決算対策、もとい駆け込みの節税対策があったらなぁ・・・なんて考えられているのではないでしょうか?
そんなわけで今回は「今からでも間に合う!現役会計事務所職員が教える法人の節税対策5選!」と題しまして駆け込み可能な法人の節税対策について解説していきたいと思います。
少額減価償却資産の特例
これはもはや定番中の定番かもしれませんが、30万円未満の物品の購入については年間300万円を限度として、購入した年度で一括で経費にすることができるという制度です。
通常10万円以上の物品を購入した場合には、「減価償却」といって分割で経費計上することになります。
分割する期間は購入した物品の内容や、その会社の業種によって異なりますが4~5年から長いものだと20年以上にわたって分割していくものもあります。
この特例を適用すると、30万円未満の物品の購入に関してはその年で一括で「減価償却」することができるため、結果として全額その年で経費にすることが可能となります。
通常の減価償却であれば購入した月(正確には事業に使い始めた月)から減価償却がスタートするため、決算期末に購入してもその年に経費にできる金額はほとんどありません。
しかしこの特例の良いところは、一括で減価償却をすることになるためたとえ決算の期末最終日であったとしても購入額全額を経費にできるというところです。
そのため定番中の定番とはいいながらも、かなり使い勝手の良い制度であることは間違いありません。
決算でそれなりの利益が見込まれるのであれば、必要なものは今期中に購入してしまいましょう!
ただし金額は30万円「未満」ですので、299,999円までとなります。
この判定の基準は経理方式が「税込経理」の場合は税込299,999円まで、「税抜経理」を採用している場合には税抜299,999円までとなりますのでその点お間違えの無いようご注意ください。
倒産防止共済への加入
続いては倒産防止共済こと「経営セーフティ共済」への加入による駆け込み節税対策になります。
「経営セーフティ共済」とは独立行政法人中小企業基盤整備機構という経済産業省が管轄する組織が提供している制度です。
趣旨としては中小企業等が取引先の破たんなどで突発的な経営危機に陥った際の資金援助などを目的とする共済制度です。
取引先の破たんにより回収不能のお金がでた場合には最大で掛金の10倍の金額まで無担保・無保証人で借入することが可能となります。
なぜこの制度が駆け込みの節税に適しているかというと、法人の場合掛金は全額損金への算入が認められています。
しかも、掛金は最大で月20万円まで掛けられて1年分を前納(一括支払)することも可能です。
すなわち、決算月であっても最大240万円の経費が作れるのです。
これは大きいですよね。ただし掛金を積むことができるのは最大で800万円までですので、3年繰り返すと240万円×3年=720万円でほぼ上限に達してしまいます。
また、掛金は全額損金算入できる一方で、解約時には受取金額の全額が収入として課税されますのでその点もお含みおきください。
決算賞与の支給(未払いも可能!)
決算間近になって、想定以上の利益が出そうな場合にはせっかくですから従業員に還元するのもひとつの手です。
従業員のモチベーションアップにも繋がりますので一石二鳥の効果が期待できます。
さらに従業員さんへの決算賞与は未払計上も可能ですので、とりあえず支給だけ決めてしまって実際の支給はあとでということも可能です。
ただし未払いとした場合には下記の条件を満たした場合のみその年度の経費とできますのでご注意ください。
- 決算の月の末日までに支給すべき従業員全員に「各人別」にその支給額を通知していること
- 決算日の末日から1か月以内に支払っていること
- 通知をした事業年度において損金経理(帳簿上経費として処理)していること
上記のすべてを満たした場合のみ、未払いでの決算賞与の経費計上が認められますので絶対にこのポイントは押さえておいてください。
また後に税務調査などを受けたときのために、決算の月の末日までに「通知」をしていた証拠として従業員の方それぞれに各人の賞与支給金額を通知した書面などを残し、署名捺印などを取受けておくと良いでしょう。
国税庁 使用人賞与の損金算入時期 こちらにも詳細が記載されていますので支給にあたって一度確認されることをオススメします。
尚、従業員さんではなく役員さんに賞与を支給する場合には期初に事前に準備しておく必要があります。その方法についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、こちらもあわせてご確認ください。
決算賞与+従業員への研修で税額控除が受けられる!
政府は働き方改革と同時に民間企業への「賃上げ」を強烈にプッシュしています。
実はこの「賃上げ」を達成した企業向けのプレゼントがあることをご存知でしょうか?
「所得拡大促進税制」という名前からして賃上げを応援する税制なのですが、
かみ砕いていうと
- 前年度の期首から今年度の期末までの24か月間ずっと給与の支給を受けた従業員の給料が前年度比1.5%増加した場合
- 前年度の役員を除く給与総額(アルバイトなども含む)から今年度の給与総額の増加分の15%を税額控除(法人税を安くする)してくれる
- さらに2.5%以上ベースアップした場合で、前年度から教育訓練費(要は研修費)が10%増加していた場合は給与総額の増加分の25%を税額控除する
という制度です。
なかなかややこしいので詳細は顧問税理士などに確認していただきたいのですが、要するに
前年より給与総額がアップしていた場合、その増加分の15%もしくは25%に相当する法人税を減税しますよ
という制度です。
わかりやすくするために「ベースアップ」という言い方をしましたが、この制度では基本給をいくら上げるなどといった制約はありません。
シンプルに年間の支給総額が増加していればOKですので、利益が出そうなときには駆け込みで決算賞与を出すことで、経費の増加とモチベーションアップとさらに税額控除まで取れるという一石三鳥を得られるチャンスです。
この節税効果はかなり大きいです。
前年度から給与総額が変わっていないと仮定すると、前年度出していない決算賞与を500万円支給することで、その節税額は法人税だけで最大125万円になります。
一般に「法人税」としてくくられているものには実は「法人税」「地方法人税」「法人事業税・地方法人特別税」「法人都道府県民税」「法人市区町村民税」と5種類の税金があります。
税額控除の対象となるのはこのなかの「法人税」だけなのですが、他の税金の一部は「法人税」額に一定の率を掛けて算出していますので節税効果はさらに大きくなります。
制度の詳細についてはこちらのパンフレットに分かりやすく説明されていますので、ぜひ一度確認してみてください。
新品160万円以上の機械装置購入で税額控除
新品で1つ160万円以上の「機械装置」を購入した場合、その購入額の7%を税額控除することができます。
例えば500万円の新品機械を購入した場合、35万円の「法人税」が控除されます。
先ほどの「所得拡大促進税制」と同様、「法人税」が安くなることで他の税金も安くなるので実際の節税額はもう少し多くなります。
また、筆者個人的には税額控除の方がオススメですが、この制度には実はもうひとつ選択肢があってそれが30%の「特別償却費」の上乗せ措置です。
減価償却費を特別に前倒しして取っていいよ
という制度になりますので、将来の経費の先取りが可能になります。
一過性の利益が出た際には特別償却の実施によって税負担を平準化させることを検討してもよいとは思いますが、そうでなければ後の経費が減少することになりますので「ご利用は計画的に」されることをオススメします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ここまで書いておいてなんですが、「節税」というと聞こえはよくても税金を減らそうと思うとそれ以上の額のお金を何らかの形で支払うしかありません。
法人の実効税率(利益に対する実際の税率)は中小企業の場合22~33%程度です。幅があるのは利益額によって大きく2段階(正確には3段階)に税率が分かれていることと、資本金や従業員の数によって変わる均等割というものがあるからです。
いずれにしても、100万円支払ってもそれによって減る税金はせいぜい33万円というところです。
すなわち残りの67万円は税金とは違う形で会社の外に出ていってしまうのです。
その67万円は本当に有効な使い方でしたか?あとで会社に収益をもたらしてくれる使い方ですか?
ここは是非とも一度立ち止まって考えていただきたい部分です。
私も担当するお客様には常にこうしたことをお話させていただいております。
税金を減らすことだけが目的になってしまっては意味がありません。
この記事を読んでもう一度、どうすれば会社のお金を最大限有効に活用できるか、その観点で自社に合うお金の使い方はどれかという視点でもう一度読み返していただければ幸いです。
会社にとって有効な使い方じゃないと思えば、100万円を残して法人税を33万円支払えば67万円のお金が手元にのこせます。無駄な100万円を外に払うくらいなら税金を払って3分の2を残す。
この選択肢も経営者として勇気ある素晴らしい決断だと思います。
節税を考えるならパートナーとなる税理士は最も重要です。
医者に「名医」や「ヤブ医者」がいるように、税理士だからといって皆がなんでも知っているわけではありません。
最適な税理士を無料で探すなら「税理士ドットコム」で探してみてはいかがでしょうか。気に入るまで何回でも無料で紹介を受けることができます。
また、「税理士ドットコム」で紹介を受けた顧客の実に71.4%の方が顧問料の引下げに成功しています。
↓↓今スグ無料で税理士を探す↓↓



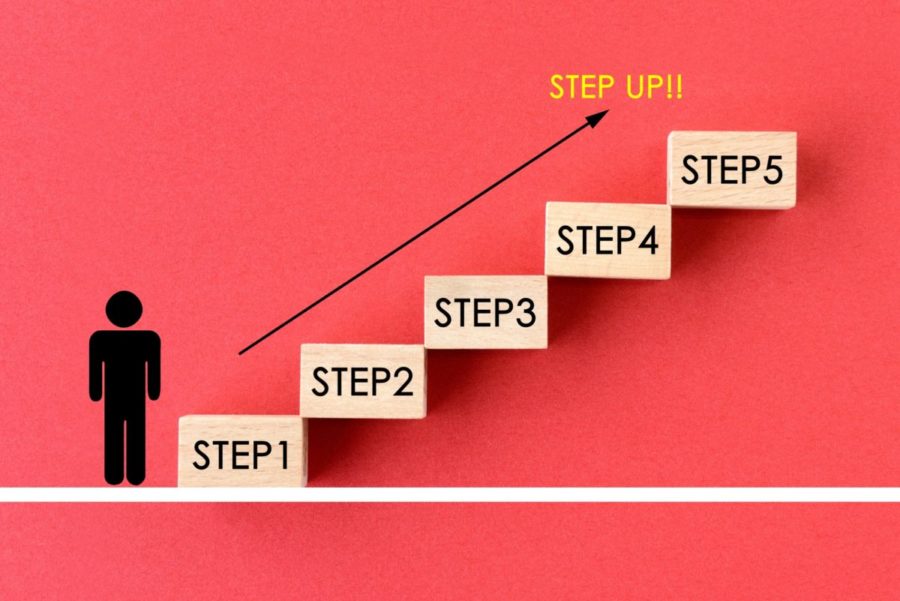







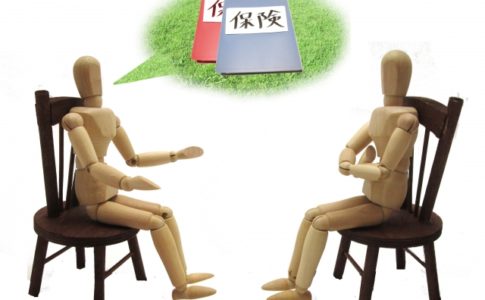


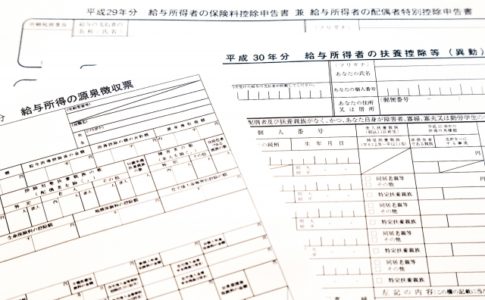

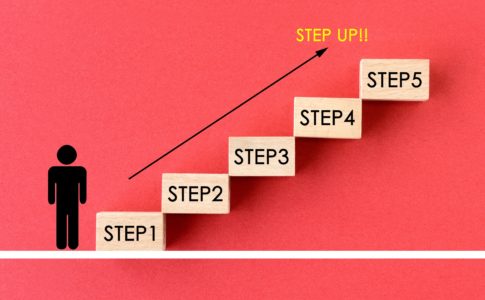



コメントを残す